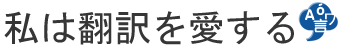- テキスト
- 歴史
星の花が降るころに安東みきえ 銀木犀の花は甘い香りで、白く小さな星の形
星の花が降るころに
安東みきえ
銀木犀の花は甘い香りで、白く小さな星の形をしている。そして雪が降るように音もなく落ちてくる。去年の秋、夏実と二人で木の真下に立ち、花が散るのを長いこと見上げていた。気がつくと、地面が白い星形でいっぱいになっていた。これじゃ踏めない、これじゃもう動けない、と夏実は幹に体を寄せ、二人で木に閉じ込められた、そう言って笑った。
──ガタン!
びっくりした。去年の秋のことをぼんやり思い出していたら、机にいきなり戸部君がぶつかってきた。戸部君は振り返ると、後ろの男子に向かってどなった。
「やめろよ。押すなよなあ。おれがわざとぶつかったみたいだろ。」
自習時間が終わり、昼休みに入った教室はがやがやしていた。
私は戸部君をにらんだ。
「なんか用?」
「宿題をきこうと思って来たんだよ。そしたらあいつらがいきなり押してきて。」
戸部君はサッカー部のだれかといつもふざけてじゃれ合っている。そしてちょっとしたこづき合いが高じてすぐに本気のけんかになる。わけがわからない。
塾のプリントを、戸部君は私の前に差し出した。
「この問題わかんねえんだよ。『あたかも』という言葉を使って文章を作りなさい、だって。おまえ得意だろ、こういうの。」
私だってわからない。いっしょだった小学生のころからわからないままだ。なんで戸部君はいつも私にからんでくるのか。なんで同じ塾に入ってくるのか。なんでサッカー部なのに先輩のように格好よくないのか。
「わかんないよ。そんなの自分で考えなよ。」
隣の教室の授業も終わったらしく、いすを引く音がガタガタと聞こえてきた。私は戸部君を押しのけるようにして立ち上がると廊下に向かった。
戸部君に関わり合っている暇はない。今日こそは仲直りをすると決めてきたのだ。はられたポスターや掲示を眺めるふりをしながら、廊下で夏実が出てくるのを待った。
夏実とは中学に上がってもずっと親友でいようと約束をしていた。だから春の間はクラスが違っても必ずいっしょに帰っていた。それなのに、何度か小さなすれ違いや誤解が重なるうち、別々に帰るようになってしまった。お互いに意地を張っていたのかもしれない。
お守りみたいな小さなビニール袋をポケットの上からそっとなでた。中には銀木犀の花が入っている。もう香りはなくなっているけれどかまわない。去年の秋、この花で何か手作りに挑戦しようと言ってそのままになっていた。香水はもう無理でも試しにせっけんを作ってみよう、そして秋になったら新しい花を拾って、それでポプリなんかも作ってみよう……そう誘ってみるつもりだった。夏実だって、私から言いだすのをきっと待っているはずだ。
夏実の姿が目に入った。教室を出てこちらに向かってくる。
そのとたん、私は自分の心臓がどこにあるのかがはっきりわかった。どきどき鳴る胸をなだめるように一つ息を吸ってはくと、ぎこちなく足を踏み出した。
「あの、夏実──」
私が声をかけたのと、隣のクラスの子が夏実に話しかけたのが同時だった。夏実は一瞬とまどったような顔でこちらを見た後、隣の子に何か答えながら私からすっと顔を背けた。そして目の前を通り過ぎて行ってしまった。音のないこま送りの映像を見ているように、変に長く感じられた。
騒々しさがやっと耳に戻ったとき、教室の中の戸部君がこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている。唇がふるえているし、目の縁が熱い。きまりが悪くてはじかれたようにその場を離れると、窓に駆け寄って下をのぞいた。裏門にも、コンクリートの通路にも人の姿はない。どこも強い日差しのせいで、色が飛んでしまったみたい。貧血を起こしたときに見える白々とした光景によく似ている。
私は外にいる友達を探しているふうに熱心に下を眺めた。本当は友達なんていないのに。夏実の他には友達とよびたい人なんてだれもいないのに。
帰りは図書委員の集まりがあったせいで遅くなった。のろのろと靴を履き替えていると、校庭からサッカー部のかけ声が聞こえてきた。
もう九月というのに、昨日も真夏日だった。校庭に出ると、毛穴という毛穴から魂がぬるぬると溶け出してしまいそうに暑かった。
運動部のみんなはサバンナの動物みたいで、入れ替わり立ち替わり水を飲みにやって来る。水飲み場の近くに座って戸部君を探した。夏実とのことを見られたのが気がかりだった。繊細さのかけらもない戸部君だから、みんなの前で何を言いだすか知れたものじゃない。どこまでわかっているのか探っておきたかった。だいたいなんであんな場面をのんびりと眺めていたのだろう。それを考えると弱みを握られた気分になり、八つ当たりとわかってもにくらしくてしかたがなかった。
戸部君の姿がやっと見つかった。
なかなか探せないはずだ。サッカーの練習をしているみんなとは離れた所で、一人ボールをみがいていた。
サッカーボールは縫い目が弱い。そこからほころびる。だからグリスをぬってやらないとだめなんだ。使いたいときだけ使って、手入れをしないでいるのはだめなんだ。いつか戸部君がそう言っていたのを思い出した。
日陰もない校庭の隅っこで背中を丸め、黙々とボールみがきをしている戸部君を見ていたら、なんだか急に自分の考えていたことがひどく小さく、くだらないことに思えてきた。
立ち上がって水道の蛇口をひねった。水をぱしゃぱしゃと顔にかけた。冷たかった。溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきたような気がした。
てのひらに水を受けて何度もほおをたたいていると、足音が近づいてきた。後ろから「おい。」と声をかけられた。戸部君だ。ずっと耳になじんでいた声だからすぐわかる。
顔をふきながら振り返ると、戸部君が言った。
「おれ、考えたんだ。」
ハンドタオルから目だけを出して戸部君を見つめた。何を言われるのか少しこわくて黙っていた。
「ほら、『あたかも』という言葉を使って文を作りなさいってやつ。」
「ああ、なんだ。あれのこと。」
「いいか、よく聞けよ……おまえはおれを意外とハンサムだと思ったことが──」にやりと笑った。「──あたかもしれない。」
やっぱり戸部君って、わけがわからない。
二人で顔を見合わせてふき出した。中学生になってちゃんと向き合ったことがなかったから気づかなかったけれど、私より低かったはずの戸部君の背はいつのまにか私よりずっと高くなっている。
私はタオルを当てて笑っていた。涙がにじんできたのはあんまり笑いすぎたせいだ、たぶん。
学校からの帰り、少し回り道をして銀木犀のある公園に立ち寄った。
銀木犀は常緑樹だから一年中葉っぱがしげっている。それをきれいに丸く刈り込むので、木の下に入れば丸屋根の部屋のようだ。夏実と私はここが大好きで、二人だけの秘密基地と決めていた。ここにいれば大丈夫、どんなことからも木が守ってくれる。そう信じていられた。
夕方に近くなっても日差しはまだ強い。木の下は陰になって涼しかった。
掃除をしているおばさんが、草むしりの手を休めて話しかけてきた。
「いい木だよねえ、こんな時期は木陰になってくれて。けど春先は、葉っぱが落ちて案外厄介なんだよ、掃除がさ。」
私は首をかしげた。常緑樹は一年中葉っぱがしげっているはずなのに。
「え、葉っぱはずっと落ちないんじゃないんですか。」
「まさか。どんどん古い葉っぱを落っことして、その代わりに新しい葉っぱを生やすんだよ。そりゃそうさ。でなきゃあんた、いくら木だって生きていけないよ。」
帽子の中の顔は暗くてよくわからなかったけれど、笑った歯だけは白く見えた。おばさんは、よいしょと言って掃除道具を抱えると公園の反対側に歩いていった。
私は真下に立って銀木犀の木を見上げた。
かたむいた陽が葉っぱの間からちらちらと差し、半円球の宙にまたたく星みたいに光っていた。
ポケットからビニール袋を取り出した。花びらは小さく縮んで、もう色がすっかりあせている。
袋の口を開けて、星形の花を土の上にぱらぱらと落とした。
ここでいつかまた夏実と花を拾える日が来るかもしれない。それとも違うだれかと拾うかもしれない。あるいはそんなことはもうしないかもしれない。
どちらだっていい。大丈夫、きっとなんとかやっていける。
私は銀木犀の木の下をくぐって出た。
安東みきえ
銀木犀の花は甘い香りで、白く小さな星の形をしている。そして雪が降るように音もなく落ちてくる。去年の秋、夏実と二人で木の真下に立ち、花が散るのを長いこと見上げていた。気がつくと、地面が白い星形でいっぱいになっていた。これじゃ踏めない、これじゃもう動けない、と夏実は幹に体を寄せ、二人で木に閉じ込められた、そう言って笑った。
──ガタン!
びっくりした。去年の秋のことをぼんやり思い出していたら、机にいきなり戸部君がぶつかってきた。戸部君は振り返ると、後ろの男子に向かってどなった。
「やめろよ。押すなよなあ。おれがわざとぶつかったみたいだろ。」
自習時間が終わり、昼休みに入った教室はがやがやしていた。
私は戸部君をにらんだ。
「なんか用?」
「宿題をきこうと思って来たんだよ。そしたらあいつらがいきなり押してきて。」
戸部君はサッカー部のだれかといつもふざけてじゃれ合っている。そしてちょっとしたこづき合いが高じてすぐに本気のけんかになる。わけがわからない。
塾のプリントを、戸部君は私の前に差し出した。
「この問題わかんねえんだよ。『あたかも』という言葉を使って文章を作りなさい、だって。おまえ得意だろ、こういうの。」
私だってわからない。いっしょだった小学生のころからわからないままだ。なんで戸部君はいつも私にからんでくるのか。なんで同じ塾に入ってくるのか。なんでサッカー部なのに先輩のように格好よくないのか。
「わかんないよ。そんなの自分で考えなよ。」
隣の教室の授業も終わったらしく、いすを引く音がガタガタと聞こえてきた。私は戸部君を押しのけるようにして立ち上がると廊下に向かった。
戸部君に関わり合っている暇はない。今日こそは仲直りをすると決めてきたのだ。はられたポスターや掲示を眺めるふりをしながら、廊下で夏実が出てくるのを待った。
夏実とは中学に上がってもずっと親友でいようと約束をしていた。だから春の間はクラスが違っても必ずいっしょに帰っていた。それなのに、何度か小さなすれ違いや誤解が重なるうち、別々に帰るようになってしまった。お互いに意地を張っていたのかもしれない。
お守りみたいな小さなビニール袋をポケットの上からそっとなでた。中には銀木犀の花が入っている。もう香りはなくなっているけれどかまわない。去年の秋、この花で何か手作りに挑戦しようと言ってそのままになっていた。香水はもう無理でも試しにせっけんを作ってみよう、そして秋になったら新しい花を拾って、それでポプリなんかも作ってみよう……そう誘ってみるつもりだった。夏実だって、私から言いだすのをきっと待っているはずだ。
夏実の姿が目に入った。教室を出てこちらに向かってくる。
そのとたん、私は自分の心臓がどこにあるのかがはっきりわかった。どきどき鳴る胸をなだめるように一つ息を吸ってはくと、ぎこちなく足を踏み出した。
「あの、夏実──」
私が声をかけたのと、隣のクラスの子が夏実に話しかけたのが同時だった。夏実は一瞬とまどったような顔でこちらを見た後、隣の子に何か答えながら私からすっと顔を背けた。そして目の前を通り過ぎて行ってしまった。音のないこま送りの映像を見ているように、変に長く感じられた。
騒々しさがやっと耳に戻ったとき、教室の中の戸部君がこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている。唇がふるえているし、目の縁が熱い。きまりが悪くてはじかれたようにその場を離れると、窓に駆け寄って下をのぞいた。裏門にも、コンクリートの通路にも人の姿はない。どこも強い日差しのせいで、色が飛んでしまったみたい。貧血を起こしたときに見える白々とした光景によく似ている。
私は外にいる友達を探しているふうに熱心に下を眺めた。本当は友達なんていないのに。夏実の他には友達とよびたい人なんてだれもいないのに。
帰りは図書委員の集まりがあったせいで遅くなった。のろのろと靴を履き替えていると、校庭からサッカー部のかけ声が聞こえてきた。
もう九月というのに、昨日も真夏日だった。校庭に出ると、毛穴という毛穴から魂がぬるぬると溶け出してしまいそうに暑かった。
運動部のみんなはサバンナの動物みたいで、入れ替わり立ち替わり水を飲みにやって来る。水飲み場の近くに座って戸部君を探した。夏実とのことを見られたのが気がかりだった。繊細さのかけらもない戸部君だから、みんなの前で何を言いだすか知れたものじゃない。どこまでわかっているのか探っておきたかった。だいたいなんであんな場面をのんびりと眺めていたのだろう。それを考えると弱みを握られた気分になり、八つ当たりとわかってもにくらしくてしかたがなかった。
戸部君の姿がやっと見つかった。
なかなか探せないはずだ。サッカーの練習をしているみんなとは離れた所で、一人ボールをみがいていた。
サッカーボールは縫い目が弱い。そこからほころびる。だからグリスをぬってやらないとだめなんだ。使いたいときだけ使って、手入れをしないでいるのはだめなんだ。いつか戸部君がそう言っていたのを思い出した。
日陰もない校庭の隅っこで背中を丸め、黙々とボールみがきをしている戸部君を見ていたら、なんだか急に自分の考えていたことがひどく小さく、くだらないことに思えてきた。
立ち上がって水道の蛇口をひねった。水をぱしゃぱしゃと顔にかけた。冷たかった。溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきたような気がした。
てのひらに水を受けて何度もほおをたたいていると、足音が近づいてきた。後ろから「おい。」と声をかけられた。戸部君だ。ずっと耳になじんでいた声だからすぐわかる。
顔をふきながら振り返ると、戸部君が言った。
「おれ、考えたんだ。」
ハンドタオルから目だけを出して戸部君を見つめた。何を言われるのか少しこわくて黙っていた。
「ほら、『あたかも』という言葉を使って文を作りなさいってやつ。」
「ああ、なんだ。あれのこと。」
「いいか、よく聞けよ……おまえはおれを意外とハンサムだと思ったことが──」にやりと笑った。「──あたかもしれない。」
やっぱり戸部君って、わけがわからない。
二人で顔を見合わせてふき出した。中学生になってちゃんと向き合ったことがなかったから気づかなかったけれど、私より低かったはずの戸部君の背はいつのまにか私よりずっと高くなっている。
私はタオルを当てて笑っていた。涙がにじんできたのはあんまり笑いすぎたせいだ、たぶん。
学校からの帰り、少し回り道をして銀木犀のある公園に立ち寄った。
銀木犀は常緑樹だから一年中葉っぱがしげっている。それをきれいに丸く刈り込むので、木の下に入れば丸屋根の部屋のようだ。夏実と私はここが大好きで、二人だけの秘密基地と決めていた。ここにいれば大丈夫、どんなことからも木が守ってくれる。そう信じていられた。
夕方に近くなっても日差しはまだ強い。木の下は陰になって涼しかった。
掃除をしているおばさんが、草むしりの手を休めて話しかけてきた。
「いい木だよねえ、こんな時期は木陰になってくれて。けど春先は、葉っぱが落ちて案外厄介なんだよ、掃除がさ。」
私は首をかしげた。常緑樹は一年中葉っぱがしげっているはずなのに。
「え、葉っぱはずっと落ちないんじゃないんですか。」
「まさか。どんどん古い葉っぱを落っことして、その代わりに新しい葉っぱを生やすんだよ。そりゃそうさ。でなきゃあんた、いくら木だって生きていけないよ。」
帽子の中の顔は暗くてよくわからなかったけれど、笑った歯だけは白く見えた。おばさんは、よいしょと言って掃除道具を抱えると公園の反対側に歩いていった。
私は真下に立って銀木犀の木を見上げた。
かたむいた陽が葉っぱの間からちらちらと差し、半円球の宙にまたたく星みたいに光っていた。
ポケットからビニール袋を取り出した。花びらは小さく縮んで、もう色がすっかりあせている。
袋の口を開けて、星形の花を土の上にぱらぱらと落とした。
ここでいつかまた夏実と花を拾える日が来るかもしれない。それとも違うだれかと拾うかもしれない。あるいはそんなことはもうしないかもしれない。
どちらだっていい。大丈夫、きっとなんとかやっていける。
私は銀木犀の木の下をくぐって出た。
0/5000
星の花が降るころに安東みきえ銀木犀の花は甘い香りで、白く小さな星の形をしている。そして雪が降るように音もなく落ちてくる。去年の秋、夏実と二人で木の真下に立ち、花が散るのを長いこと見上げていた。気がつくと、地面が白い星形でいっぱいになっていた。これじゃ踏めない、これじゃもう動けない、と夏実は幹に体を寄せ、二人で木に閉じ込められた、そう言って笑った。──ガタン!びっくりした。去年の秋のことをぼんやり思い出していたら、机にいきなり戸部君がぶつかってきた。戸部君は振り返ると、後ろの男子に向かってどなった。「やめろよ。押すなよなあ。おれがわざとぶつかったみたいだろ。」自習時間が終わり、昼休みに入った教室はがやがやしていた。私は戸部君をにらんだ。「なんか用?」「宿題をきこうと思って来たんだよ。そしたらあいつらがいきなり押してきて。」戸部君はサッカー部のだれかといつもふざけてじゃれ合っている。そしてちょっとしたこづき合いが高じてすぐに本気のけんかになる。わけがわからない。塾のプリントを、戸部君は私の前に差し出した。「この問題わかんねえんだよ。『あたかも』という言葉を使って文章を作りなさい、だって。おまえ得意だろ、こういうの。」私だってわからない。いっしょだった小学生のころからわからないままだ。なんで戸部君はいつも私にからんでくるのか。なんで同じ塾に入ってくるのか。なんでサッカー部なのに先輩のように格好よくないのか。「わかんないよ。そんなの自分で考えなよ。」隣の教室の授業も終わったらしく、いすを引く音がガタガタと聞こえてきた。私は戸部君を押しのけるようにして立ち上がると廊下に向かった。戸部君に関わり合っている暇はない。今日こそは仲直りをすると決めてきたのだ。はられたポスターや掲示を眺めるふりをしながら、廊下で夏実が出てくるのを待った。夏実とは中学に上がってもずっと親友でいようと約束をしていた。だから春の間はクラスが違っても必ずいっしょに帰っていた。それなのに、何度か小さなすれ違いや誤解が重なるうち、別々に帰るようになってしまった。お互いに意地を張っていたのかもしれない。お守りみたいな小さなビニール袋をポケットの上からそっとなでた。中には銀木犀の花が入っている。もう香りはなくなっているけれどかまわない。去年の秋、この花で何か手作りに挑戦しようと言ってそのままになっていた。香水はもう無理でも試しにせっけんを作ってみよう、そして秋になったら新しい花を拾って、それでポプリなんかも作ってみよう.そう誘ってみるつもりだった。夏実だって、私から言いだすのをきっと待っているはずだ。夏実の姿が目に入った。教室を出てこちらに向かってくる。そのとたん、私は自分の心臓がどこにあるのかがはっきりわかった。どきどき鳴る胸をなだめるように一つ息を吸ってはくと、ぎこちなく足を踏み出した。「あの、夏実──」私が声をかけたのと、隣のクラスの子が夏実に話しかけたのが同時だった。夏実は一瞬とまどったような顔でこちらを見た後、隣の子に何か答えながら私からすっと顔を背けた。そして目の前を通り過ぎて行ってしまった。音のないこま送りの映像を見ているように、変に長く感じられた。騒々しさがやっと耳に戻ったとき、教室の中の戸部君がこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている。唇がふるえているし、目の縁が熱い。きまりが悪くてはじかれたようにその場を離れると、窓に駆け寄って下をのぞいた。裏門にも、コンクリートの通路にも人の姿はない。どこも強い日差しのせいで、色が飛んでしまったみたい。貧血を起こしたときに見える白々とした光景によく似ている。私は外にいる友達を探しているふうに熱心に下を眺めた。本当は友達なんていないのに。夏実の他には友達とよびたい人なんてだれもいないのに。 帰りは図書委員の集まりがあったせいで遅くなった。のろのろと靴を履き替えていると、校庭からサッカー部のかけ声が聞こえてきた。もう九月というのに、昨日も真夏日だった。校庭に出ると、毛穴という毛穴から魂がぬるぬると溶け出してしまいそうに暑かった。運動部のみんなはサバンナの動物みたいで、入れ替わり立ち替わり水を飲みにやって来る。水飲み場の近くに座って戸部君を探した。夏実とのことを見られたのが気がかりだった。繊細さのかけらもない戸部君だから、みんなの前で何を言いだすか知れたものじゃない。どこまでわかっているのか探っておきたかった。だいたいなんであんな場面をのんびりと眺めていたのだろう。それを考えると弱みを握られた気分になり、八つ当たりとわかってもにくらしくてしかたがなかった。戸部君の姿がやっと見つかった。なかなか探せないはずだ。サッカーの練習をしているみんなとは離れた所で、一人ボールをみがいていた。サッカーボールは縫い目が弱い。そこからほころびる。だからグリスをぬってやらないとだめなんだ。使いたいときだけ使って、手入れをしないでいるのはだめなんだ。いつか戸部君がそう言っていたのを思い出した。日陰もない校庭の隅っこで背中を丸め、黙々とボールみがきをしている戸部君を見ていたら、なんだか急に自分の考えていたことがひどく小さく、くだらないことに思えてきた。 立ち上がって水道の蛇口をひねった。水をぱしゃぱしゃと顔にかけた。冷たかった。溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきたような気がした。 てのひらに水を受けて何度もほおをたたいていると、足音が近づいてきた。後ろから「おい。」と声をかけられた。戸部君だ。ずっと耳になじんでいた声だからすぐわかる。 顔をふきながら振り返ると、戸部君が言った。「おれ、考えたんだ。」 ハンドタオルから目だけを出して戸部君を見つめた。何を言われるのか少しこわくて黙っていた。「ほら、『あたかも』という言葉を使って文を作りなさいってやつ。」「ああ、なんだ。あれのこと。」「いいか、よく聞けよ……おまえはおれを意外とハンサムだと思ったことが──」にやりと笑った。「──あたかもしれない。」 やっぱり戸部君って、わけがわからない。 二人で顔を見合わせてふき出した。中学生になってちゃんと向き合ったことがなかったから気づかなかったけれど、私より低かったはずの戸部君の背はいつのまにか私よりずっと高くなっている。 私はタオルを当てて笑っていた。涙がにじんできたのはあんまり笑いすぎたせいだ、たぶん。 学校からの帰り、少し回り道をして銀木犀のある公園に立ち寄った。 銀木犀は常緑樹だから一年中葉っぱがしげっている。それをきれいに丸く刈り込むので、木の下に入れば丸屋根の部屋のようだ。夏実と私はここが大好きで、二人だけの秘密基地と決めていた。ここにいれば大丈夫、どんなことからも木が守ってくれる。そう信じていられた。 夕方に近くなっても日差しはまだ強い。木の下は陰になって涼しかった。 掃除をしているおばさんが、草むしりの手を休めて話しかけてきた。「いい木だよねえ、こんな時期は木陰になってくれて。けど春先は、葉っぱが落ちて案外厄介なんだよ、掃除がさ。」 私は首をかしげた。常緑樹は一年中葉っぱがしげっているはずなのに。「え、葉っぱはずっと落ちないんじゃないんですか。」「まさか。どんどん古い葉っぱを落っことして、その代わりに新しい葉っぱを生やすんだよ。そりゃそうさ。でなきゃあんた、いくら木だって生きていけないよ。」 帽子の中の顔は暗くてよくわからなかったけれど、笑った歯だけは白く見えた。おばさんは、よいしょと言って掃除道具を抱えると公園の反対側に歩いていった。 私は真下に立って銀木犀の木を見上げた。 かたむいた陽が葉っぱの間からちらちらと差し、半円球の宙にまたたく星みたいに光っていた。 ポケットからビニール袋を取り出した。花びらは小さく縮んで、もう色がすっかりあせている。 袋の口を開けて、星形の花を土の上にぱらぱらと落とした。 ここでいつかまた夏実と花を拾える日が来るかもしれない。それとも違うだれかと拾うかもしれない。あるいはそんなことはもうしないかもしれない。 どちらだっていい。大丈夫、きっとなんとかやっていける。 私は銀木犀の木の下をくぐって出た。
翻訳されて、しばらくお待ちください..
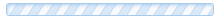
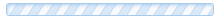
星の花が降るころに
安東みきえ銀木犀の花は甘い香りで、白く小さな星の形をしている。そして雪が降るように音もなく落ちてくる。去年の秋、夏実と二人で木の真下に立ち、花が散るのを長いこと見上げていた。気がつくと、地面が白い星形でいっぱいになっていた。これじゃ踏めない、これじゃもう動けない、と夏実は幹に体を寄せ、二人で木に閉じ込められた、そう言って笑った。──ガタン!びっくりした。去年の秋のことをぼんやり思い出していたら、机にいきなり戸部君がぶつかってきた。戸部君は振り返ると、後ろの男子に向かってどなった。「やめろよ。押すなよなあ。おれがわざとぶつかったみたいだろ。」自習時間が終わり、昼休みに入った教室はがやがやしていた。私は戸部君をにらんだ。「なんか用?」「宿題をきこうと思って来たんだよ。そしたらあいつらがいきなり押してきて。」戸部君はサッカー部のだれかといつもふざけてじゃれ合っている。そしてちょっとしたこづき合いが高じてすぐに本気のけんかになる。わけがわからない。塾のプリントを、戸部君は私の前に差し出した。「この問題わかんねえんだよ。『あたかも』という言葉を使って文章を作りなさい、だって。おまえ得意だろ、こういうの。」私だってわからない。いっしょだった小学生のころからわからないままだ。なんで戸部君はいつも私にからんでくるのか。なんで同じ塾に入ってくるのか。なんでサッカー部なのに先輩のように格好よくないのか。「わかんないよ。そんなの自分で考えなよ。」隣の教室の授業も終わったらしく、いすを引く音がガタガタと聞こえてきた。私は戸部君を押しのけるようにして立ち上がると廊下に向かった。戸部君に関わり合っている暇はない。今日こそは仲直りをすると決めてきたのだ。はられたポスターや掲示を眺めるふりをしながら、廊下で夏実が出てくるのを待った。夏実とは中学に上がってもずっと親友でいようと約束をしていた。だから春の間はクラスが違っても必ずいっしょに帰っていた。それなのに、何度か小さなすれ違いや誤解が重なるうち、別々に帰るようになってしまった。お互いに意地を張っていたのかもしれない。お守りみたいな小さなビニール袋をポケットの上からそっとなでた。中には銀木犀の花が入っている。もう香りはなくなっているけれどかまわない。去年の秋、この花で何か手作りに挑戦しようと言ってそのままになっていた。香水はもう無理でも試しにせっけんを作ってみよう、そして秋になったら新しい花を拾って、それでポプリなんかも作ってみよう……そう誘ってみるつもりだった。夏実だって、私から言いだすのをきっと待っているはずだ。夏実の姿が目に入った。教室を出てこちらに向かってくる。そのとたん、私は自分の心臓がどこにあるのかがはっきりわかった。どきどき鳴る胸をなだめるように一つ息を吸ってはくと、ぎこちなく足を踏み出した。「あの、夏実──」私が声をかけたのと、隣のクラスの子が夏実に話しかけたのが同時だった。夏実は一瞬とまどったような顔でこちらを見た後、隣の子に何か答えながら私からすっと顔を背けた。そして目の前を通り過ぎて行ってしまった。音のないこま送りの映像を見ているように、変に長く感じられた。騒々しさがやっと耳に戻ったとき、教室の中の戸部君がこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている。唇がふるえているし、目の縁が熱い。きまりが悪くてはじかれたようにその場を離れると、窓に駆け寄って下をのぞいた。裏門にも、コンクリートの通路にも人の姿はない。どこも強い日差しのせいで、色が飛んでしまったみたい。貧血を起こしたときに見える白々とした光景によく似ている。私は外にいる友達を探しているふうに熱心に下を眺めた。本当は友達なんていないのに。夏実の他には友達とよびたい人なんてだれもいないのに。帰りは図書委員の集まりがあったせいで遅くなった。のろのろと靴を履き替えていると、校庭からサッカー部のかけ声が聞こえてきた。もう九月というのに、昨日も真夏日だった。校庭に出ると、毛穴という毛穴から魂がぬるぬると溶け出してしまいそうに暑かった。運動部のみんなはサバンナの動物みたいで、入れ替わり立ち替わり水を飲みにやって来る。水飲み場の近くに座って戸部君を探した。夏実とのことを見られたのが気がかりだった。繊細さのかけらもない戸部君だから、みんなの前で何を言いだすか知れたものじゃない。どこまでわかっているのか探っておきたかった。だいたいなんであんな場面をのんびりと眺めていたのだろう。それを考えると弱みを握られた気分になり、八つ当たりとわかってもにくらしくてしかたがなかった。戸部君の姿がやっと見つかった。なかなか探せないはずだ。サッカーの練習をしているみんなとは離れた所で、一人ボールをみがいていた。サッカーボールは縫い目が弱い。そこからほころびる。だからグリスをぬってやらないとだめなんだ。使いたいときだけ使って、手入れをしないでいるのはだめなんだ。いつか戸部君がそう言っていたのを思い出した。日陰もない校庭の隅っこで背中を丸め、黙々とボールみがきをしている戸部君を見ていたら、なんだか急に自分の考えていたことがひどく小さく、くだらないことに思えてきた。立ち上がって水道の蛇口をひねった。水をぱしゃぱしゃと顔にかけた。冷たかった。溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきたような気がした。てのひらに水を受けて何度もほおをたたいていると、足音が近づいてきた。後ろから「おい。」と声をかけられた。戸部君だ。ずっと耳になじんでいた声だからすぐわかる。顔をふきながら振り返ると、戸部君が言った。「おれ、考えたんだ。」ハンドタオルから目だけを出して戸部君を見つめた。何を言われるのか少しこわくて黙っていた。「ほら、『あたかも』という言葉を使って文を作りなさいってやつ。」「ああ、なんだ。あれのこと。」「いいか、よく聞けよ……おまえはおれを意外とハンサムだと思ったことが──」にやりと笑った。「──あたかもしれない。」やっぱり戸部君って、わけがわからない。二人で顔を見合わせてふき出した。中学生になってちゃんと向き合ったことがなかったから気づかなかったけれど、私より低かったはずの戸部君の背はいつのまにか私よりずっと高くなっている。私はタオルを当てて笑っていた。涙がにじんできたのはあんまり笑いすぎたせいだ、たぶん。学校からの帰り、少し回り道をして銀木犀のある公園に立ち寄った。銀木犀は常緑樹だから一年中葉っぱがしげっている。それをきれいに丸く刈り込むので、木の下に入れば丸屋根の部屋のようだ。夏実と私はここが大好きで、二人だけの秘密基地と決めていた。ここにいれば大丈夫、どんなことからも木が守ってくれる。そう信じていられた。夕方に近くなっても日差しはまだ強い。木の下は陰になって涼しかった。掃除をしているおばさんが、草むしりの手を休めて話しかけてきた。「いい木だよねえ、こんな時期は木陰になってくれて。けど春先は、葉っぱが落ちて案外厄介なんだよ、掃除がさ。」私は首をかしげた。常緑樹は一年中葉っぱがしげっているはずなのに。「え、葉っぱはずっと落ちないんじゃないんですか。」「まさか。どんどん古い葉っぱを落っことして、その代わりに新しい葉っぱを生やすんだよ。そりゃそうさ。でなきゃあんた、いくら木だって生きていけないよ。」帽子の中の顔は暗くてよくわからなかったけれど、笑った歯だけは白く見えた。おばさんは、よいしょと言って掃除道具を抱えると公園の反対側に歩いていった。私は真下に立って銀木犀の木を見上げた。かたむいた陽が葉っぱの間からちらちらと差し、半円球の宙にまたたく星みたいに光っていた。ポケットからビニール袋を取り出した。花びらは小さく縮んで、もう色がすっかりあせている。袋の口を開けて、星形の花を土の上にぱらぱらと落とした。ここでいつかまた夏実と花を拾える日が来るかもしれない。それとも違うだれかと拾うかもしれない。あるいはそんなことはもうしないかもしれない。どちらだっていい。大丈夫、きっとなんとかやっていける。私は銀木犀の木の下をくぐって出た。
安東みきえ銀木犀の花は甘い香りで、白く小さな星の形をしている。そして雪が降るように音もなく落ちてくる。去年の秋、夏実と二人で木の真下に立ち、花が散るのを長いこと見上げていた。気がつくと、地面が白い星形でいっぱいになっていた。これじゃ踏めない、これじゃもう動けない、と夏実は幹に体を寄せ、二人で木に閉じ込められた、そう言って笑った。──ガタン!びっくりした。去年の秋のことをぼんやり思い出していたら、机にいきなり戸部君がぶつかってきた。戸部君は振り返ると、後ろの男子に向かってどなった。「やめろよ。押すなよなあ。おれがわざとぶつかったみたいだろ。」自習時間が終わり、昼休みに入った教室はがやがやしていた。私は戸部君をにらんだ。「なんか用?」「宿題をきこうと思って来たんだよ。そしたらあいつらがいきなり押してきて。」戸部君はサッカー部のだれかといつもふざけてじゃれ合っている。そしてちょっとしたこづき合いが高じてすぐに本気のけんかになる。わけがわからない。塾のプリントを、戸部君は私の前に差し出した。「この問題わかんねえんだよ。『あたかも』という言葉を使って文章を作りなさい、だって。おまえ得意だろ、こういうの。」私だってわからない。いっしょだった小学生のころからわからないままだ。なんで戸部君はいつも私にからんでくるのか。なんで同じ塾に入ってくるのか。なんでサッカー部なのに先輩のように格好よくないのか。「わかんないよ。そんなの自分で考えなよ。」隣の教室の授業も終わったらしく、いすを引く音がガタガタと聞こえてきた。私は戸部君を押しのけるようにして立ち上がると廊下に向かった。戸部君に関わり合っている暇はない。今日こそは仲直りをすると決めてきたのだ。はられたポスターや掲示を眺めるふりをしながら、廊下で夏実が出てくるのを待った。夏実とは中学に上がってもずっと親友でいようと約束をしていた。だから春の間はクラスが違っても必ずいっしょに帰っていた。それなのに、何度か小さなすれ違いや誤解が重なるうち、別々に帰るようになってしまった。お互いに意地を張っていたのかもしれない。お守りみたいな小さなビニール袋をポケットの上からそっとなでた。中には銀木犀の花が入っている。もう香りはなくなっているけれどかまわない。去年の秋、この花で何か手作りに挑戦しようと言ってそのままになっていた。香水はもう無理でも試しにせっけんを作ってみよう、そして秋になったら新しい花を拾って、それでポプリなんかも作ってみよう……そう誘ってみるつもりだった。夏実だって、私から言いだすのをきっと待っているはずだ。夏実の姿が目に入った。教室を出てこちらに向かってくる。そのとたん、私は自分の心臓がどこにあるのかがはっきりわかった。どきどき鳴る胸をなだめるように一つ息を吸ってはくと、ぎこちなく足を踏み出した。「あの、夏実──」私が声をかけたのと、隣のクラスの子が夏実に話しかけたのが同時だった。夏実は一瞬とまどったような顔でこちらを見た後、隣の子に何か答えながら私からすっと顔を背けた。そして目の前を通り過ぎて行ってしまった。音のないこま送りの映像を見ているように、変に長く感じられた。騒々しさがやっと耳に戻ったとき、教室の中の戸部君がこちらを見ていることに気づいた。私はきっとひどい顔をしている。唇がふるえているし、目の縁が熱い。きまりが悪くてはじかれたようにその場を離れると、窓に駆け寄って下をのぞいた。裏門にも、コンクリートの通路にも人の姿はない。どこも強い日差しのせいで、色が飛んでしまったみたい。貧血を起こしたときに見える白々とした光景によく似ている。私は外にいる友達を探しているふうに熱心に下を眺めた。本当は友達なんていないのに。夏実の他には友達とよびたい人なんてだれもいないのに。帰りは図書委員の集まりがあったせいで遅くなった。のろのろと靴を履き替えていると、校庭からサッカー部のかけ声が聞こえてきた。もう九月というのに、昨日も真夏日だった。校庭に出ると、毛穴という毛穴から魂がぬるぬると溶け出してしまいそうに暑かった。運動部のみんなはサバンナの動物みたいで、入れ替わり立ち替わり水を飲みにやって来る。水飲み場の近くに座って戸部君を探した。夏実とのことを見られたのが気がかりだった。繊細さのかけらもない戸部君だから、みんなの前で何を言いだすか知れたものじゃない。どこまでわかっているのか探っておきたかった。だいたいなんであんな場面をのんびりと眺めていたのだろう。それを考えると弱みを握られた気分になり、八つ当たりとわかってもにくらしくてしかたがなかった。戸部君の姿がやっと見つかった。なかなか探せないはずだ。サッカーの練習をしているみんなとは離れた所で、一人ボールをみがいていた。サッカーボールは縫い目が弱い。そこからほころびる。だからグリスをぬってやらないとだめなんだ。使いたいときだけ使って、手入れをしないでいるのはだめなんだ。いつか戸部君がそう言っていたのを思い出した。日陰もない校庭の隅っこで背中を丸め、黙々とボールみがきをしている戸部君を見ていたら、なんだか急に自分の考えていたことがひどく小さく、くだらないことに思えてきた。立ち上がって水道の蛇口をひねった。水をぱしゃぱしゃと顔にかけた。冷たかった。溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと顔の輪郭が戻ってきたような気がした。てのひらに水を受けて何度もほおをたたいていると、足音が近づいてきた。後ろから「おい。」と声をかけられた。戸部君だ。ずっと耳になじんでいた声だからすぐわかる。顔をふきながら振り返ると、戸部君が言った。「おれ、考えたんだ。」ハンドタオルから目だけを出して戸部君を見つめた。何を言われるのか少しこわくて黙っていた。「ほら、『あたかも』という言葉を使って文を作りなさいってやつ。」「ああ、なんだ。あれのこと。」「いいか、よく聞けよ……おまえはおれを意外とハンサムだと思ったことが──」にやりと笑った。「──あたかもしれない。」やっぱり戸部君って、わけがわからない。二人で顔を見合わせてふき出した。中学生になってちゃんと向き合ったことがなかったから気づかなかったけれど、私より低かったはずの戸部君の背はいつのまにか私よりずっと高くなっている。私はタオルを当てて笑っていた。涙がにじんできたのはあんまり笑いすぎたせいだ、たぶん。学校からの帰り、少し回り道をして銀木犀のある公園に立ち寄った。銀木犀は常緑樹だから一年中葉っぱがしげっている。それをきれいに丸く刈り込むので、木の下に入れば丸屋根の部屋のようだ。夏実と私はここが大好きで、二人だけの秘密基地と決めていた。ここにいれば大丈夫、どんなことからも木が守ってくれる。そう信じていられた。夕方に近くなっても日差しはまだ強い。木の下は陰になって涼しかった。掃除をしているおばさんが、草むしりの手を休めて話しかけてきた。「いい木だよねえ、こんな時期は木陰になってくれて。けど春先は、葉っぱが落ちて案外厄介なんだよ、掃除がさ。」私は首をかしげた。常緑樹は一年中葉っぱがしげっているはずなのに。「え、葉っぱはずっと落ちないんじゃないんですか。」「まさか。どんどん古い葉っぱを落っことして、その代わりに新しい葉っぱを生やすんだよ。そりゃそうさ。でなきゃあんた、いくら木だって生きていけないよ。」帽子の中の顔は暗くてよくわからなかったけれど、笑った歯だけは白く見えた。おばさんは、よいしょと言って掃除道具を抱えると公園の反対側に歩いていった。私は真下に立って銀木犀の木を見上げた。かたむいた陽が葉っぱの間からちらちらと差し、半円球の宙にまたたく星みたいに光っていた。ポケットからビニール袋を取り出した。花びらは小さく縮んで、もう色がすっかりあせている。袋の口を開けて、星形の花を土の上にぱらぱらと落とした。ここでいつかまた夏実と花を拾える日が来るかもしれない。それとも違うだれかと拾うかもしれない。あるいはそんなことはもうしないかもしれない。どちらだっていい。大丈夫、きっとなんとかやっていける。私は銀木犀の木の下をくぐって出た。
翻訳されて、しばらくお待ちください..
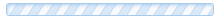
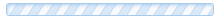
星の花が降るころに安東みきえ
a. 銀木犀の花は甘い香りで 、 ゙ 白く小さな星の形をしているそして雪が降るように音もなく落ちてくる去年の秋 ー 、 夏実と二人で木の真下に立ち 、 ゙ 花が散るのを長いこと見上げていた気がつくと 、 ゙ 地面が白い星形でいっぱいになっていたこれじゃ踏めないこれじゃもう動けない 、 、 、 と夏実は幹に体を寄せ二人で木に閉じ込められた 、 ゙ そう言って笑った
-- ガタンバドミントン├ BWF スーパーシリーズ└その他
びっくりした。去年の秋のことをぼんやり思い出していたら 、 ゙ 机にいきなり戸部君がぶつかってきた戸部君は振り返ると 、 ゙ 後ろの男子に向かってどなった
」やめろよ ゙ ー 押すなよなあおれがわざとぶつかったみたいだろ ゙ 顛自習時間が終わり 、 ゙ 昼休みに入った教室はがやがやしていた
私は戸部君をにらんだ ー
」なんか用和室の「
」宿題をきこうと思って来たんだよ ゙ ー そしたらあいつらがいきなり押してきて。
ー 戸部君はサッカー部のだれかといつもふざけてじゃれ合っているそしてちょっとしたこづき合いが高じてすぐに本気のけんかになる ゙ ー わけがわからない
塾のプリントを 、 ゙ 戸部君は私の前に差し出した
」この問題わかんねえんだよ テ ゙ ー 」「あたかもという言葉を使って文章を作りなさい 、 ー だって 、 おまえ得意だろこういうの ゙ 顛私だってわからない ゙ ー いっしょだった小学生のころからわからないままだ
翻訳されて、しばらくお待ちください..
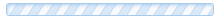
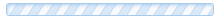
他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.
- I have problem
- Cras numquam scire
- I have problem
- In November I am busy, I am looking forw
- 給与
- In November I am busy, I am looking forw
- ប្រាក់បៀវត្ស
- 戦争が終わった後の若者に希望を持たせるために
- Lusa hari apa?
- moon grin
- Oman viihtyisän huoneen,jossa kylpyhoune
- 戦争が終わった後の若者に希望を持たせるためにできた
- Quomodo in corpore est morbus, est vitiu
- 検査OK品棚に置かれた製品の【移動表】に前工程のサインが入っていることを確認。梱
- et leur apprendrai é avoir l'air' fabule
- わが友よ
- 若者に希望を持たせるために
- 幻覚
- それはできた
- I have problem
- Quomodo in corpore est morbus, est vitiu
- 幻覚
- I have problem
- Quomodo in corpore est morbus, est vitiu